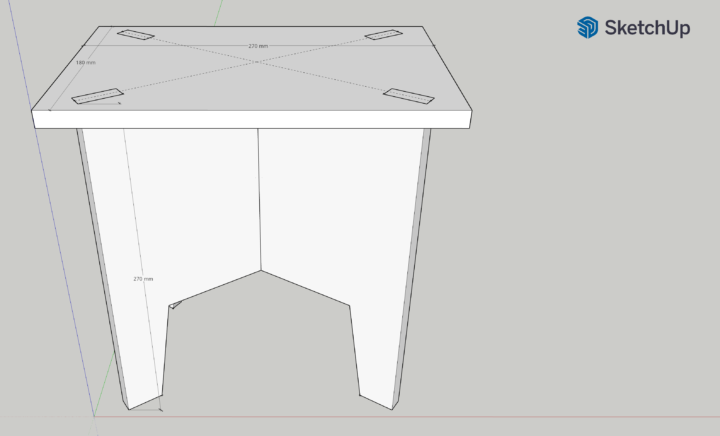前回、苦労して材料を部屋まで運び込んだ当プロジェクト。あとはもうやるだけです。
ブログの更新は日が空いてしまいましたが、実際は同じ週末での話です。
自分にしては珍しく、材料購入から施工まで一気に進めました。ブログは遅れましたが。
畳上げ
何はともあれ、まずは、現状の畳をどかすところから。
縁にマイナスドライバー差し込んで、いよっと持ち上げれば外れます。畳は特に固定されていないので、その重みとピッチリとした寸法で収まっています。なので、重さにさえ勝てれば外れます。
ちゃんと測ってはいませんが、多分10数キロくらいあると思います。重いし大きいしで疲れます。腰には要注意。

奥に立ててあるのが畳で、見えているのが畳の裏側になります。
床は合板になっています。割りと埃っぽく見えますが、実際はサッと掃除機かけたあとなので、元々の合板自体が…汚れている?でもカビや傷みがなかったので良かったです。このまま施工できます。
根太の施工
まずは、根太の施工を行います。ねだって読むらしいです。でもGoogle日本語入力では、ねぶとじゃないと変換できない。
ホームセンターで杉の30x40mmで2mくらいの6本束で売っていました。確か1,600円くらい。ふだん面取りされている2×4とかに慣れていると、かなり角が尖っているというか、四角!という印象を受けました。
これを、部屋の外周に沿って敷き、その後は約30cm間隔で並べていきます。約30cmというのは、3×6の合板を載せたとき、隣り合う合板のエッジがどちらも根太に乗るようにするためです。

部屋のサイズに対して、長さが足りないので、2本つなぐことになります。構造的な強度は不要と判断したので、端材で横から止めました。

根太より高さが出てしまうと、上に乗せる合板がガタつくので要注意です。
また、本来は根太の上からビスを打って、下地の合板と固定します。
でも、下地の合板は物件のものだな、と思ったので固定していません。外枠と内側に並べた根太は金折で固定してみました。(写真なかった)
断熱材(スタイロフォーム)の施工
根太が並べ終われば、スタイロフォームを詰めていきます。これが結構楽しい作業でした。
スタイロフォームは発泡スチロールなので、カッターで切れます。厚みが30mmあるので、ちょっと長めにカッターの刃を出しますので、怪我しないように注意です。
現物合わせでサイズ測って、カッターで切って根太の隙間に押し込みます。ぴったり入ると気持ちいい。色々参考にしたブログなんかでも気持ちいいって書いてありましたが、同感です。

断熱性を上げるなら、根太との隙間を気密テープで塞ぐのもありだそうですが、そのままにしました。本当はやろうと思っていたのに、今の今まで忘れてました。
根太のつなぎ目は端材が飛び出ているので、その分スタイロフォームも切り欠けを作ります。

OSB合板の施工
これはもう並べるだけです。根太が正しく施工できていれば、OSB合板がきれいに根太を跨ぐ形になるはずです。
ただ、合板を置いてしまうと、根太の位置がわからなくなります。本当はちゃんとOSB合板にも墨付けして、とか思っていたけど、面倒になったので壁にだけ印つけて、目分量でやっちゃいました。
壁に印を付ける方法は、先人の知恵です。Thanks。

最初はマスキングテープに矢印書いて貼ってたけど、斜めに貼れば良いじゃん!と気付いたときは天才かと思いました。
まずは3×6そのままのサイズで並べ、半端な部分は丸ノコでカット。長尺のカットは難しかったです。
OSBカットして並べたら、あとはビス止めです。35mmのビスを使いました。根太に合わせて約30cm間隔で止めました。頭が浮いちゃうと、やっぱり上に乗せる合板に影響がでるので、めり込むように。
使った電ドラはマキタの10.8vです。プロはインパクト使うんでしょうが、自分にはこれで十分な気がしました。掃除機とバッテリー共用できるのも良いです!
それでもOSBが5枚分、いっぱいビス打ちました!

そして同様の作業をもう一度。OSB合板の重なりが揃わないように、さっき半端だった方に3×6そのままを。そしてビスを打ちまくる!

間違い探しですね笑。ちょっと隙間が目立っているので、分かりますね。
これで、根太で30mm、OSBの9mm x2で48mmになったはずです。
おわりに
ここまでくれば、あとはフローリングだけです。ちょっと疲れたので、引っ張って別記事にします。
こういう作業をしていると、Youtubeで見たプロの方は、やっぱ上手だなって思います。作業がスムーズで、迷いがない。
自分はスタイロ切りすぎたり、丸ノコでのカットが斜めになったり、OSBの上でビスが見にくくて踏んで痛かったり、色々やりました。楽しいです。